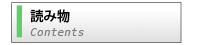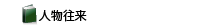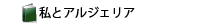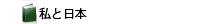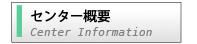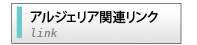金井勝彦(IHIパリ事務所)
1970年3月初旬のある日の午後、春はまだ浅いが太陽の光が輝くアルジェ空港に降り立ちました。これが私のアルジェリアへの第一歩で、そして始めての海外出張でした。その後長くアルジェリアと係わるなんて当時は考えてもいませんでしたが、その日の私は嬉しさで少し興奮もしていました。
それは学生時代に読んだカミュの「エトランジェ」、フランス留学時代に知り合ったアルジェリア人学生からの断片的な知識等で、「行ってみたい国」と漠然と考えていた事が本当に実現したからです。
アルジェリアへの渡航は工事派遣でした。その半年前の1969年9月にソナトラックと交わした契約でスキクダにLPG生産工場を建設する事になり、私はアドミの業務で対客先折衝、通関業務、諸官庁からの許認可の取得等を行なう為に派遣されたのですが、実際は初年兵よろしく何でもやらねばならず、やらされました。電話の通じないあの頃はタクシーを呼ぶのに50分も歩いて迎えに行かねばならない状況でした。 部下のアルジェリア人に頼むと2-3時間も帰って来ないからです。 また夜には、日本人の大先輩の夕食のお世話もしなくてはなりません。レストランを探し、メニューの選択を手伝う事など寝るとき以外は仕事みたいなものでした。しかし先輩達はよく怒りもしましたが、仕事も良く教えて呉れました。今日の私はアルジェリアが育ててくれたと言っても過言では有りません。

(2000年10月末 アルズー/LNGジャンボ・プロジェクト引渡し式の記念撮影)
アルジェは坂の多い街です。地中海に面した街は、アルジェ・ブランシュと言われました。かっては紺碧の海に映える白い美しい街並だっただろう事が容易に想像されましたが、70年のあの頃は、白い建物もくすんで汚れていました。アルジェリア独立戦争の爪痕が残っていたのです。しかし、街は活気に溢れてれていました。街は若者が元気に闊歩しており、看板は全てフランス語、デパートには沢山の商品が並んでおり、食料品も豊富で肉屋には外人用のブタ肉も売っていました。映画「望郷(ペペルモコ)」で有名なホテル・アレッテイにはカジノもありました。デイデイッシュ・ムラッド通りを上って行くと右側に「クートビア」と言うキャバレーがありベリーダンスも見る事が出来たのです。当時は赴任直後で相場も解らず、始めてのアラブの踊りに魅了され帰る時には貰ったばかりの仮払金の大半を置いて来たほろ苦い思い出があります。
仕事はアルジェとスキクダでしたが、仕事量の多い現場のあるスキクダで大半を過ごしました。アルジェではお客さんのソナトラックや関係官庁に書類を届け後日それを引き取りに行くと言う単調だが忍耐の居る仕事でした。あの頃のアルジェは日本人の数も少なく街で見かけることは余り有りません。スキクダは現場ゆえに、ひとたび工事が開始されると周囲の風景が変わって行くので建設工事の素晴らしさに感動したものです。
スキクダは田舎でしたが、新しい港の建設工事、発電所やLNG工場の新設などで、フランス人、ドイツ人、チェコ人等外国人が沢山居りました。日本人はわが社のたったの8人だけでアルジェリア人にとっては見た事もないから最初の一年間はシノワ(中国人)と呼ばれ続けました。スキクダには当時ソマルガスというフランスとアルジェリアの合弁企業があって、総裁がクワニイさん(後のソナトラック副総裁)、工場長がカジタニさん(ENIP総裁)でした。工事期間中お客の若いプロマネとよく揉めましたが、この工場長が仲介に入り解決させてくれました。カジタニさんの言葉で「ラクダは、自分の瘤は見えない」とアルジェリアの諺を教えて戴いた事が忘れられません。このソマルガスでは、フランスのテクニップが建設中のLNGプラント3系列が最後のテストに入る段階で、LNG工場から送られて来る混合ガスをブタンとプロパンに分離するのがLPG工場なのです。このソマルガスも他の石油施設と共に1972年2月24日に国有化され今日のソナトラックとなっているのです。
私の一回目のアルジェリア滞在は3年1ヶ月後の73年4月迄でこの間ニクソンショックもありました。二回目は駐在員として78年8月末に赴任し3年7ヵ月後の82年4月迄滞在しました。この2回の滞在期間の間にアルジェリアは大きく変わりました。最初の時は生活物資も豊富にあったし、各役所にはコーペランと呼ぶフランス人がアドバイザーとして居り、権限はなかったが打ち合わせはそれなりに進みました。78年の時は極端にイスラム化が進み、首都アルジェの名前さえ変わり、道路標識もアラブ語で表示され生活物資に事欠く状況でした。将に振り子が180度振れたのでアルジェリアに対するイメージに驚いたものです。こうした変化に戸惑いを感じるのは我々があくまでも訪問者の立場に他ならないからです。独立後10年余を経てアルジェリアは真の独立を目指し、自分達自身の手で国を立ち上げようと苦悩した時が70年代後半から始まったのではないでしょうか。
会社は、アルジェリアからほぼ連続して仕事を戴いております。1978年末のアルズー・ジャンボLPGプラント建設工事契約以来小さな保守工事等を入れるとほとんど途切れることなくわが社の誰かがアルジェリアに滞在しております。アルジェリアに一度足を踏み入れると何故かなかなか足を洗えません。将にやくざの世界みたいなものです。わが社に限らず他のメーカーも商社も、フランス語要員が足りないのか育てていないのか地中海を挟んでアルジェとパリに勤務すると言う会社が多いようで、会社を超えて家族付き合いをしている人達が多いようです。これ
もアルジェリアが仲人してくれた人生の賜物と思います。確かに彼の地では苦労しました。日本に居ればしなくて済んだ苦労も有ります。そうした経験を共有した仲間意識がお互いを結び付ける絆となっているのでしょう。

(2000年10月末 アルズー/LNGジャンボ・プロジェクト 左から3番目が金井さん)
テロに揺れた90年代前半からの時期にまたアルズーでLPG工場拡張工事を行ないました。私はこの時パリからの出張で現場に度々行きました。安全問題で厳しい状況の時期ゆえに現場に長期出張している人々は、サイト外のアルジェリア人の生活に触れる機会もなく、唯宿舎と現場を往復する生活だけに、サイトを離れる時は残る同僚に後ろめたさを感じたものです。しかし、スキクダで逢った若きアルジェリア人のエンジニアも、今ではソナトラックの大幹部へと昇進していましたが、逢うと20年余の時間を超えて高校時代の同級生に会ったように抱擁してくるので、仕事を超えて友人に逢えた友情を感じました。
ソナトラックとの仕事を通じてアルジェリアを見るとアルジェリアの人々は本当に大きく成長したと思います。下請工場で働く職工の技量そのものは、日本人のそれと比較しても何ら変らない人が多く育っている事を実感しました。環境と待遇を考えてあげれば、今後そうした人間が数多く増えて来るであろうし、その時には日本の加工外注の拠点になる事も夢ではありません。 ミドルクラスまでの技術レベルは心配ないが上層レベルのマネージメント能力のアップと謙虚さを身につければもっと大きく飛躍できるものと思います。アルジェリアに最初に旅をしてから30年経ちましたが、アルジェリア人の顔が何時も明るいのは不思議と思っていましたが、これはアルジェリア人がくよくよしない明日があると言う前向きの性格なのではないかと思われます。
初のアルジェリア・サハラ滞在を終えて
2002年2月14日 記
明治大学大学院研究生
大月美恵子
今回の私のアルジェリア滞在は、国連大学の小堀巖教授がトヨタ財団の助成の下計画した学術調査に、記録係として参加を許されたことで実現した。
最終目的地は、小堀教授が1961年から永きにわたり定点調査を続けておられるイン・ベルベル(Inbelbel)という、人口1,000人ほどのごく小さなオアシス集落で、首都アルジェよりはマリとの国境の方が近い。
イン・ベルベルは本当に遠い。どの位遠いかというと、単に「沙漠のただ中に浮かぶかのようなオアシス」と表現しただけでは物足りないほど遠い。まず、首都アルジェから空路アドラール(Adrar アドラール県・県都)までが約1,000キロ、ここから陸路200キロほど南下し、仏軍が原爆実験を行ったレガンヌ(Regane)の手前で東に折れると小1時間ほどでアウレフという街に着く(Aoulef郡・郡都)。ここまでは舗装道路が整っている。ここまで来れば目的地のイン・ベルベルまでは120キロ程であるが、アウレフから先は道がない。ないけれどあるらしい。これは仏語でピスト(Piste)と呼ばれ、道端にポツポツと古タイヤの道標が続いている周りは誰でもそれとわかるが、何の目印もなくなると私の目には周囲との区別が付かなくなる。今回はアウレフとイン・ベルベルの間を2往復したが、運転手のマフメットさんは決して道程を間違えることなく4度が4度とも同じ休憩地点を通過した。
 さて、イン・ベルベルでの生活であるが、小堀教授が折りに触れ学術的な側面だけでなく、村や人々の様子について繰り返し話して下さったせいか、まるで初めて来た所という気がしなかった。だから、サハラはすごい所だ、とさんざん脅かしてくれた教授の期待を裏切って申し訳ないが、毎日毎食のクスクスにも、露天のトイレにもさして驚きはしなかった。ギョッとしたことと言えば、朝、顔を洗う時にお湯とともに洗濯用粉石鹸を差し出されたことと、村外れを歩いていると、そこかしこで無造作に捨てられた羊の頭や、時には丸ごとの死体に出くわしたことくらいなものである。
さて、イン・ベルベルでの生活であるが、小堀教授が折りに触れ学術的な側面だけでなく、村や人々の様子について繰り返し話して下さったせいか、まるで初めて来た所という気がしなかった。だから、サハラはすごい所だ、とさんざん脅かしてくれた教授の期待を裏切って申し訳ないが、毎日毎食のクスクスにも、露天のトイレにもさして驚きはしなかった。ギョッとしたことと言えば、朝、顔を洗う時にお湯とともに洗濯用粉石鹸を差し出されたことと、村外れを歩いていると、そこかしこで無造作に捨てられた羊の頭や、時には丸ごとの死体に出くわしたことくらいなものである。
イン・ベルベルでは、動物の死体は腐るということがないらしい。カラカラに干からびて風に吹かれてころがって行くうちに、少しずつ千切れていつか砂に紛れてしまうだけだ。それでも小堀教授らが泊まったザウィーア(各集落に設けられた公共宿泊施設、巡礼などの旅人が泊まる)の向かいの農園の垣のかげで、育たなかった真っ白な毛の子羊のまだ新しい死体を見つけたときはさすがにかわいそうにと思った。
しかし、私たちが毎日イン・ベルベルで食べていたのは、そうして屍を晒していた羊たちの肉である。ここでは動物はタンパク源に他ならず、それ以上でもそれ以下でもない。日々自分の生命をつなぐために、他の色々の生き物を犠牲にしているということは、分かっているつもりであったが、今回のイン・ベルベルでの生活でほど身に沁みたことはなかった。

ところで日本を発つ前、小堀教授は私にこうもおっしゃられた。サハラでは万事がゆっくりで、仕事の合間の時間はたっぷりある、と。私は素直にこの言葉を信じ、スケッチブックと奮発して24色の色鉛筆と、稲垣足穂の本を買って、彼の地に臨んだ。昼は沙漠とナツメ椰子のある風景を写生し、夜は満天の星空をひとしきり眺めてから宿に戻って薄暗い灯の下で足穂を読んだなら,さぞかし趣があるだろうと思って。ところが実際に事が終わってみると、出来たスケッチはわずか5枚、本は1ページも読み進んでいなかった。
これは小堀教授が嘘をついたわけでなく、今回はLe japonais d'InBelbel というタイトルの映画の撮影部隊が同行したせいである。撮る方と撮られる方総勢8名の闖入者がゾロゾロとうろつきまわったのであるから、アウレフでもさることながら、さらに小さいイン・ベルベルの住民の方々にはずいぶんご迷惑をおかけした。アルジェリアは日本ではアラブ圏の一国として認識されているが、アウレフ、イン・ベルベルを含むアドラール県の人口のマジョリティはサハラ特有の皮膚の黒い人々なので、日本人の私達はもとより、北部のアルジェから行った映画会社のスタッフも、現地の人々にとっては異色な感じがしたことと思う。

話は戻って、Le japonais d'Inbelbelの le japonais とはむろん小堀教授のことである。ことは、2000年3月、アルジェリアの仏語紙ル・マタンが「40年間アルジェリア・サハラの研究を続けている日本人」について1ページほどの記事を掲載したことに始まるが、これにProcom International社のナディア・シェラビ氏が関心を寄せ、当時の渡辺伸アルジェリア大使が、両者の橋渡しの労をとって下さったことによって現実のものとなった。
映画とはいっても映画館で上映される商業用映画ではなく小堀教授がワンシーンのために何度も演技をさせ直させられたとか、その演技ぶりが本物の俳優顔負けだったとか逆に大根だったとか、そういうエピソードはない。今回撮影を行ったProcom社は主に、日本で言えば岩波映画であるとか、NHK特集のようなドキュメンタリーフィルムを手がけるプロダクションで、撮影もごく淡々と、小堀教授と長年の現地調査協力者のハジ氏の作業風景をフィルムに納めていくと言った感じで、各シーンはものすごく地味である。加えて、主役の小堀教授がカメラがまわっている時といない時とで何の変わりもないのだからなおさらであろう。
しかし、演技っ気はなくとも、アウレフやイン・ベルベルの農園のナツメヤシの木陰で話し合っている小堀教授とハジ氏は不思議と絵になっていた。これは、この40年間に10何回か繰り返した現地調査の苦楽の経験を共有する両人だからこそ醸し出せる雰囲気であり、たとえどんな名優が演技したとしても追いつくものではないと思えた。
 初めてサハラに降り立った翌日、アドラールからアウレフに向かって車が走り出した時、"膝が痛い"、車窓から差し込んでくるサハラの日差しはちょうど脚にあたってそんな風に感じられた。あれはたった一ヶ月弱前のことであるのに、彼の地で会った人達皆がすでに懐かしくてならない。
初めてサハラに降り立った翌日、アドラールからアウレフに向かって車が走り出した時、"膝が痛い"、車窓から差し込んでくるサハラの日差しはちょうど脚にあたってそんな風に感じられた。あれはたった一ヶ月弱前のことであるのに、彼の地で会った人達皆がすでに懐かしくてならない。
アラブの餡パン
Madame・Chibi・Hangai
出来上がったあんぱんとお友達
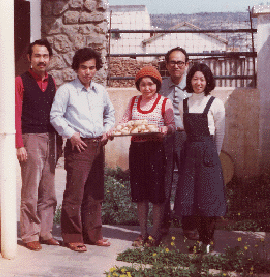 炊事、洗濯、食材の買出しの毎日を過ごしていた或る日、町のパン屋さんにお願いして餡パンを焼いて貰いました。事の始まりは折に触れ、我が家で拵えていた小麦饅頭からでした。私が何時もバケットパン、ケーキ、ボンボン等を買い求めるパン屋さんで、「日本にはお饅頭と言お菓子があって、とても美味しい。それは姿、形が若干違うが日本全国何処でも売っている。」と、得々と話した上、今度来る時プレゼントする約束をして帰りました。
炊事、洗濯、食材の買出しの毎日を過ごしていた或る日、町のパン屋さんにお願いして餡パンを焼いて貰いました。事の始まりは折に触れ、我が家で拵えていた小麦饅頭からでした。私が何時もバケットパン、ケーキ、ボンボン等を買い求めるパン屋さんで、「日本にはお饅頭と言お菓子があって、とても美味しい。それは姿、形が若干違うが日本全国何処でも売っている。」と、得々と話した上、今度来る時プレゼントする約束をして帰りました。
私の拵えるお饅頭は、生のイースト菌が此方でも手に入るので、小麦粉に若干のイースト菌を混ぜ、一晩寝かせて置きます。餡は、小豆の代用に此方で売っている大きさ八ミリ、厚さ三ミリ程の豆です。煮ると柔らかく煮えますので、これにお砂糖を加え煮詰めます。お砂糖は輸入品ですが、比較的安く買えるので惜しげなく使えます。餡は難を言えば色が薄茶ですので、これも此方で手に入る食紅を使いアンコ色に工夫していました。蒸は深鍋に網(主殿が手に入れてくれた金網)をひいて蒸し揚げて置きますと、事務所から帰った主殿はご飯前と言うのに三個程平らげてくれます。
或る日、中近東の取材に来られた新聞社の論説委員の方が、現場の取材と在留の皆さんの生活状況の取材を終えてお帰りになる時、無理矢理お持ち帰り頂き、オランのホテルで食べた感想文を、《アラブで食べた日本のお袋のお饅頭》と、題して朝日ジャーナルに掲載された記事を、《変わり行くアラブ》と言う本と一緒に贈って頂きました。
この様な曰く因縁のあるお饅頭をパン屋さんの親父さんに、私の思惑もあって試食してもらいました。其の時の親父さんは、お世辞かどうか解かりませんでしたが、満更でもない顔つきでした。そこで私は本題に入りました。
「日本にはこの甘い所が入ったパンがある。私はそれが作りたい協力して下さい。」
と、頼み込みパン生地を別けて貰い、序にパンを焼く時に使う平たい鉄板を借り受け、お友達の手を煩わし、アルジェリア始まって以来の餡パン造りに兆戦を始めました。
ここアルジェリアのパンは、バケットパンで、太さ五センチ程、長さ三十五センチ程の大きさで、一般家庭の食事に供する物で、表面の焼きかげんは、日本の食パン、菓子パンと違い比較的硬く焼いてあります。私達も最初の内は硬くて食べるのに馴染めなかったが、慣れるとアルジェリアの味で中々の物でした。
フランスパンの生地も、焼き上げる鉄板も借りる事が出来、お友達のお手伝いもあり、少々小振りでしたが、まあ〜まあ〜の出来具合に仕上がりました。それを借りて来た鉄板の上に並べ、パン屋さんに運び込みました。近所の顔見知りの子供たちは、日本の小母さんが何か拵えて来たばかり、
「何だ。何だ。」
と三、四人で付いて来ました。私も得意になって、
「ジャポンのガトウーだ、これからパン屋さんで焼いて貰うのだ。」
と、主殿と二人で運び込みました。
いよいよ試食の段階が来ました。日本人の奥様方五人で試食して見ましたが、皮はフランスパンと同じく硬かったのですが、中の餡は甘くトレビアンでした。早速パン屋さんの親父さんにも試食して貰いました。初めて食べる日本の餡パンを複雑な面持ちで、餡を指差して、
「これはトレビアンだ。然し生地には塩が入っているから堅くなる、砂糖を入れれば柔らかくなると思う。」
と、アドバイスしてくれました。
折角ここまで出来たのだからこの次はパン屋さんの助言を生かして、柔らかいアルジェリアの始めての餡パンに再度兆戦して、主殿を喜ばしてあげたいと願っています。
Fin