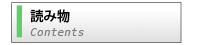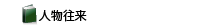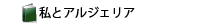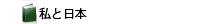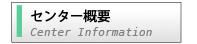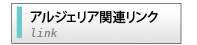2001.9.28
財団法人名古屋国際センター
交流協力課長
星野 寛行
私ども名古屋国際センターは、1984年に外務大臣の許可により名古屋市が設立した公益法人であり、設立以来、市民レベルの国際交流を促進するために様々な事業を行ってきております。
主な事業として7言語での海外情報の提供、ボランティア団体の活動支援、各種の国際交流・協力事業の実施等がありますが、その中で、全国的にも余り例がない制度として「なごや民間大使」という制度があります。 この制度は日本に在住経験のある外国人を、当センターが特別嘱託員として2名を1年間委嘱し、母国紹介事業の企画などをしていただくもので、これまでに1985年の初代のガーナ以来、計27ヶ国、28人の「なごや民間大使」が就任しております。
現在は、第27代のアルジェリア、第28代のフィリピンの民間大使が活動しておりますが、先日、9月14日〜16日の3日間にわたりアルジェリアのラムダニ・ザイラが母国紹介イベントとして企画した「アルジェリア・フェスティバル」を開催いたしました。 このフェスティバルでは、アマール・ベンジャマ駐日アルジェリア大使、前駐アルジェリア日本大使であり現在は日本アルジェリアセンター代表の渡辺伸様をお迎えしてのオープニング式典を始めとし、アマール・ベンジャマ大使の講演、コンサート、観光と文化の映像を使っての紹介、映画、料理教室等を行った他、常設展示として美術工芸品、民族衣裳、写真の展示、世界遺産である「タッシリ・ナジェール」の紹介、アラビア文字教室等を設けるなど多角的にアルジェリアを紹介させていただきました。
日本からかなり遠いということもあり日頃、知る機会が極めて少なくミステリアスな印象を受けるアルジェリアに対し、市民の関心は非常に高く、お陰をもちまして実に多くの方々にご来場いただきました。 中でも、アマール・ベンジャマ大使を囲んでの立食懇談会は、直接、大使とお話ができたため市民の方々に大変、好評でした。

「このフェスティバルに参加したことにより、アルジェリアが身近になった。もっと知りたい。」との声が多くの方から寄せられたことは、主催者として嬉しい限りでありますが、一方でフェスティバル開催までの経緯は決して順調ではありませんでした。日本とアルジェリアの関係は政治、経済、文化等あらゆる面において活発とは言いがたく、日本在住のアルジェリア人もわずか約150人に過ぎないため、他国のフェスティバルであれば容易に準備できることが、今回はとても難しく直前まで、四苦八苦の連続でした。それでも最終的に多くの方々に参加いただけるようなフェスティバルを催せたのは一重に、関係者の方々の並々ならぬご尽力によるものであったと思います。
アマール・ベンジャマ大使を始めとするアルジェリア大使館の皆様、ファリード・アイワシュ様(名古屋在住のアルジェリア人)、カメール・ブラベル様(東京在住のアルジェリア人)、渡辺様・・・・・・・・・・これらの方々のアルジェリアへの愛情なくしてはできなかったことが数多くあり、このフェスティバルに対する熱意を肌で感じた3日間でした。 大変恐縮ですが、この場をお借りして、改めて御礼申しあげます。 ラムダニ・ザイラは残念ながらこの9月末をもって、アルジェリア・フェスティバルという大きなプレゼントを名古屋市民に残し、1年間の任期を終えます。
当センターは、これからも引き続き、各国のなごや民間大使を迎えてまいりますが、何年後かには2人目のアルジェリアのなごや民間大使が生まれているかも知れません。
その時には、アルジェリアが「遠くて近い国」となっていることを期待して止みません。そして、そのキッカケの一つが今回のフェスティバルとなっていれば・・・・・・・・・・。
アルジェリアの漁業振興
平成13年8月31日
(株)ジェイエスエム
吉田光彦

縁があり1984年より8年余りの駐在を経て、その後出張ベースでアルジェリアの仕事をさせて頂き早いもので17年の月日が流れた。
その間アルジェリアは原理主義の問題など幾多の困難に遭いながらも、私にとって非常に懐の深い魅力に満ちた国であり続けた。かけがえのない多くの友人に恵まれたことが、この国が私をここまで強く惹きつけてやまない大きな理由である。そんな私の最近の仕事のひとつに漁業振興のサポートがある。
アルジェリアは、1280KMの海岸線を有するにもかかわらず、現在年間漁獲高約10万トン、近隣のモロッコ70万トン、フランス54万トンと比較すると寂しい数字である。
 もともと漁業振興に目を向けたのは、現地にて漁業関係者とのコンタクトを行なう中で、魚網、エンジン、航海計器類その他漁業用器材の販売不振の理由を分析した結果、それら漁業用器材の老朽化のため思い通り操業ができない事、また、主に個人で活動している現地漁民が器材調達・収穫物現金化の両面で厳しい環境に置かれている事が明白になったためである。
もともと漁業振興に目を向けたのは、現地にて漁業関係者とのコンタクトを行なう中で、魚網、エンジン、航海計器類その他漁業用器材の販売不振の理由を分析した結果、それら漁業用器材の老朽化のため思い通り操業ができない事、また、主に個人で活動している現地漁民が器材調達・収穫物現金化の両面で厳しい環境に置かれている事が明白になったためである。
アルジェリアの漁業分野は、独立後、炭化水素分野、重工業政策の推進に邁進した結果、日の目を見ない分野となり、1980年代までの独占輸入公団による漁業用器材の買付け以後、政府の資金はほとんど注入されず他の分野に比べ遅れた分野となっている。
このことの抜本的改善に向けての対策実施は民間ベースでは、限界があることから渡辺前大使にお伺いして漁業振興を日本・アルジェリア政府のプロジェクトにするべく色々とアドバイスを頂き助けていただいた。
アルジェリアの水産省側も昨年1月に今までの農林水産省の一部門から省に格上げされ、水産大臣を始め各局長クラスのアルジェリア漁業を良くしていこうという熱意がひしひしと感じられ、しかも、漁業先進国である日本のノウハウを取り入れたいというアルジェリア側の意向を非常に強く感じる。
しかしながら、現時点ではアルジェリア側の治安状況が不安定であることから、彼らの熱意に応えて現地に乗り込むことが容易ではないのが実情である。
現地側からは、海洋調査分野、漁業教育分野など具体的案件があがっており、逆転の発想で水産省の漁業行政官を数名日本に招待して漁業行政トレーニングのプロポーザルをだせるところまでこぎつけた。このことがアルジェリア漁業育成の一助になればと考えている。一方、世界各地の漁業フィールドにて魚のキャッチングから流通までの指導をおこなっている国内メーカーのノウハウを十分活用させていただき、まず初期段階として個人での活動でなく漁民の組織化を根付かせるため、アルジェリア各地の漁港を廻りセミナーなどの活動をおこなっている。
アルジェリアは今年からICCATに加盟し、日本からマグロ漁船も入るようになってきているが、アルジェリア政府の方針にもなっている炭化水素部門以外の産業育成・失業者対策という観点から、また、現在WHOで定めている魚の1人当たりの年間消費量6.2KG(現在アルジェリアの1人当たりの年間消費量は3.2KG)を達成するためにもアルジェリア漁業振興のために今後も活動を進めていく所存である。
在アルジェリア日本人会便り
2001年 9月24日
アルジェリア日本人会会長
山口哲朗
1. 在パリ アルジェリア日本人会時代(1994年-2000年)
1993年年末、外国人を標的にしたテロによる治安悪化により、首都アルジェ市に滞在していた日本民間企業のほとんどの方々はアルジェリア国外に退避されました。
1994年になり、パリに退避された有志の方々の"アルジェリア日本人会を続けよう"との掛け声の下、在パリ アルジェリア日本人会と言う呼称での継続を決定。 参加企業はパリ在住のアルジェリアに関連する企業・政府関係団体の皆様で、その数は15を超えました。
主な活動は、この時代アルジェリアに残られた日本大使館の方(主に大使閣下)がパリに立ち寄られる機会を捉え、現地の状況をお聞きすると言うもの。
荒大使閣下時代(1994年-96年)は3-6ヶ月に一度の会合。 渡辺大使閣下時代は(1996年-2000年)には1-3ヶ月と言う頻度で皆様が集まり、 お話をする機会がありました。
日ア両国間の経済活動の停滞していた時代にも拘らず、常時15名以上の 御出席があり、大きな個室の少ないパリで会場確保で幹事の方が御苦労された と言うエピソードもなつかしく思い出されます。
又この在パリ アルジェリア日本人会が継続できましたのも、荒大使閣下、渡辺大使閣下及び大使館の方々皆様の御協力のお陰であり、この紙面をお借りして 改めて御礼を申し上げたいと思います。
2. 在アルジェリア日本人会の復活(2001年1月以降)
2000年よりアルジェ市駐在を再開する企業が見られ、2001年に入り5商社・ 2メーカーの7企業がアルジェ市への駐在復帰を決めました。 渡辺大使閣下の強い後押しもあり、2001年1月10日に、なんと7年以上振りに、 復活 在アルジェリア日本人会の第1回目の会合をアルジェ市で開く事が出来ました。
この9月までに既に6回の会合を開催し、駐在復帰後の各社共通問題点・ 日本大使館館からの治安状況を含む連絡等の議題をこなしております。 8月には浦辺 新大使閣下も御着任され、アルジェリア日本人会名誉会長にも御就任が 決まっておられます。 9月には更に1商社のアルジェ市駐在復活も決まっており、在アルジェリア日本人会も徐々に活気を帯びてくるものと期待しております。
3. 日本大使館のテニスコート開放

このアルジェリア日本人会の復活に合わせるように、渡辺大使閣下御配慮により 毎週木曜日午後に日本大使館内のテニスコートを日本人会に開放していただいきました。 木々の緑に囲まれたすがすがしいクレーコートで、毎週木曜日各社テニス好きの方々の歓声、笑い声が日本大使館の中で聞かれております。
又,日本大使館の方もコートに立ち寄られ(残念ながら木曜は大使館のみ就業日) 治安情勢等現地状況確認の絶好の場所となっております。
日本・アルジェリアのテニス対抗戦を開こうとのお話もあり、今後もこの木曜テニスはリクリエイションのみならず真剣な練習の場として続いてくれると思って おります。

私とアルジェリア
恵泉女学園大学教授
宮治一雄
私が、はじめてアルジェリアの土を踏んだのは、1968年3月末であった。
農業省付属の研究所に席を置いて、自主管理農場についての調査に取り組むことになった。
当時は、独立直後の混乱から経済が回復していず、オイルブームも国民生活にまで及んでいなかった。人々は貧しかったけれども、独立したことに誇りを抱き前途に大きな希望をもっていた。その時は一年半滞在したが、その後も二回長期滞在したので、合算すると四年間くらい滞在したことになる。商社の方々などに比べるとごく短いが、研究者としては一番長いのではなかろうか。
知り合った人々からよく質問されたのは、なぜアルジェリアに関心をもったか? ということだった。
これは、みずからも自問し続けた問いであるが、その10年前、1958年に東京外大のフランス科に入学したことが契機であったことは疑いない。この年は、アルジェリア戦争が原因でフランス第四共和制が崩壊しドゴールが登場した年であり、日本でもアルジェリア関連記事が新聞をにぎわせ、FLNの極東代表部が活動したり、アルジェリア関連の書物が発行されたりしていた時期だった。
先輩の谷口脩さん(元読売新聞社、現富山国際大学)に、アジア・アフリカ連帯会議主催の講演会に連れていってもらい、淡徳三郎さん(『アルジェリア革命』などの著者)や鈴木道彦さん(J・ロワ『アルジェリア戦争』の訳者)に紹介してもらったりして、アルジェリアの勉強をはじめた。
大学につづいて大学院を出た後、アジア経済研究所に勤務し、同研究所から派遣されたのが、10年後の68年ということになる。
以来、40年以上、アルジェリアに加えて、両隣のチュニジア・モロッコを含むマグレブ諸国の研究を続けてきた。というと聞こえはよいが、マグレブ諸国を生計の源としてきたといったほうが正確だろう。
大学の教員になってからも、講義のなかでついついマグレブ諸国のことを話してしまう。アルジェリアのためになることをしてきたというよりも、アルジェリアによって生きて来たことを痛感している。
それだけにアルジェリア・センターの設立をきっかけにして、アルジェリアの人々にどういうふうに恩返しをすればよいかと考えているところである。
変化しゆく国に通いつめて
在セネガル日本国大使館
一等書記官 兼 医務官
勝田 吉彰
私は在フランス日本国大使館の医務官として前任地パリに勤務していた頃、その職務の一 環として在アルジェリア日本国大使館への巡回検診として定期的にアルジェを訪れる機会 に恵まれた。
医務官としての職務だから、その本旨は大使館員のみなさんの健康管理、つまり診察や 血液検査・尿検査、保健指導といった事を2泊3日のタイトな日程でこなしてとんぼ帰り してくる…というものだから、基本的には"空港と大使館"だけの訪問である。
このような 訪問形態はアルジェリアに限ったことではなく、ガボン・カメルーン・コンゴ民主共和国 といった国々についても同様なのであるが、アルジェリアに関しては特に印象が強く、格 別の思い入れを感じるのである。
当時のパスポートのビザ欄をめくって、赤いアルジェリアの入国ビザを数えてみると 、6回分押されている。初回は1996年、最終回は2000年である。 初訪問の96年、アルジェリアはテロリストの活躍最盛期であった。当時パリからの直 行便は運行停止され、行きも帰りもそれぞれ隣国チュニジアで1泊しての遠回りを強いら れた。
空港に着くと銃を持参の警備員にぴったりガードされ、囮と共に2台1組で猛スピ ードで疾駆する防弾車のスリルを味わうという、到着早々から他の巡回先では期待すべく もない経験が出来た上、高い塀と無数の監視カメラで守られた大使館コンパウンドに入る と、その分厚い鉄扉は固く閉ざされて帰りの日まで食べる時も寝る時も含めて一切外出不可となったが、しかしそれだけに館員の皆さんとは三食を共にして密接に接し、興味深き話を多々聞くことが出来た。
小生が到着する前日に空港管制塔に迫撃弾が打ち込まれた話 や市場の真ん中で爆弾が連発する話などは、窓外から聞こえてくる銃声のBGMによりリアリティーがぐっと増し、下手な怪談よりはるかに背筋を冷やしてくれるものであった。
もともとの本職は精神科医(精神保健指定医)で ある私は、未知の国を訪れると、その国の精神病院の見学をおねだりするのを楽しみにし ている。しかしこの国では、病院テロなるものが横行し、早い話、爆弾を積んだ"ニセ救急車"が病院敷地に侵入してドカン!というのが流行っていたので医療機関の視察は避けるべきことであった。
こういった環境下で職務に邁進される館員の皆さんの心理的ストレス状況は想像に難く なく、そのフォローは極めて重要な任務の一つであった。 そのようなおどろおどろしい雰囲気で始まった私のアルジェ通いであったが、ブーテフ リカ政権の誕生を境にして、回を追うごとに変化が見られるようになってきた。
99年あたりからは、空港送迎の防弾車はいつしか囮の1台がなくなり小生が乗車する 車の単独走行となり、その走りっぷりも、超特急から急行程度に、"形相変えた全力疾走" から、中央車線の車の流れとも協調できるものとなっていった。
仕事を終わり夜更けのグ ラスを傾けながらの語らいも、銃声のBGMは聞こえなくなり、心地よい酔いを自然に楽 しめる時間となっていった。
その次の訪問からは、昼食ぐらいは外出も可能になり、アルジェ訪問5回目にして初め て空港ー大使館線以外の車窓をめでることができた。
この街が緑豊かな美しき場所であるというのはこの5回目にして初めての発見であった 。車窓を説明してくれる同乗者によるガイドは「ここは銃撃事件の現場だった」「ここは 車爆弾で○人亡くなった現場」etc…と、ありがちな観光ガイドとはおよそかけ離れた内 容が続いたが、表面的に眺める限り日々の営みは粛々と流れているように観察された。

そして2000年に入り最後の巡回では、夜は大使館敷地から出て市中のホテルに宿泊 するという革命的(?)なことが可能になった。用意されたホテルは、敷地入口で車のトランクを開けさせて爆発物チェックをする強面ガードマンや玄関先でピーピー音をたてる 金属探知器といった少々ユニークな舞台小道具が気分を盛り上げてくれるけれども、これらを通過したあとはごく快適な四つ星ホテルであった。
緑豊かな中庭にはのどかな雰囲気 が流れ、昼下がりのカフェを楽しみつつ周囲のテーブルを眺め回してみると、ビジネスス ーツに身を包んだ英語、ドイツ語、フランス語の集団が三々五々、ポータブルパソコンを たたきながら何組もミーティングをしている。アルジェリアに平安の兆し(及びそれがも たらすであろう利権)を嗅ぎつけた目ざとい集団 が早くも蠢き始めている現場…・ということのようであった。
セネガルへの転勤辞令により、2000年前半で終了したアルジェ通いであったが 、「政権の変わった国」「変化しゆく国」というものを、時系列を追って観察する機会に 恵まれたのは僥倖の限りであり、実に面白い体験であった。特にアルジェリアにおいては 、日常何げない所に"変化"を肌で感じることが出来(この点、同じ巡回検診先かつ「政権 の変わった国」という条件を満たしながらも終始同様の光景が目についたコンゴ民主共和 国あたりと対称をなす)、小生の思い入れもひとしおである。
その後聞くところによれば、パリからアルジェへの直行便も再開され、小生の後任者は チュニジア経由の遠回りを強いられることなく、2時間あまりのフライトで欧州内路線の ような気軽さでアルジェ入りしているようである。
さらに5年後、10年後、この国が「この仕事をしているのでなければ、まず訪れるこ とのない国」ではなくなり、アルジェ空港のロビーにお揃いのバッジをつけた日本人の一 行が闊歩し、"出国カードの書き方"を添乗員が大声で説明する…・といった光景が現れる日を期待したい。
その時には、小生ももう一度その場に降り立ち、「昔々自動小銃を持っ た軍隊が立っていた場所」や「かつて若かりし頃、防弾車に押し込まれて全力疾走した高速道路」で再びの感傷にひたってみたいと思っている。
砂漠とシャケ弁当
日揮(株)アルジェリア事業部長
小野照政
(編集部:本原稿はISEP〈石油開発情報センター)発行の「ISEPニュース」2001年12月号用に書かれたものであるが、著者及びISEPのご好意により本JOURNALに転載させていただくものである)
今日もまたアルジェ発ハッシメサウド行きのエアーアルジェリー(アルジェリアの国営航空会社)の一番機に乗った。
アトラス山脈を越え真っ直ぐ南下し、眼下に黒煙をあげる工場群が見えると機体は降下を開始する。

ハッシ・ルメルのプラント
アルジェリアで治安が悪化し国内移動に飛行機を使いはじめて8年余になるが、 思い起こせばアルジェリアでの仕事はまさに距離との戦いであった。
最初の南部でのプロジェクトは76年のハッシロンメルにて開始された。ピーク時には日本人約2500人、アルジェリア人5000人以上が働いており、それまでは小さな天然ガスの処理プラントがあっただけのハッシ・ロンメル村は瞬く間に小さな町を形成していった。
約5000人のアルジェリア人の殆どは近くの(と言っても100キロメートル程離れているが)町から大型バスにて通勤してきていた。
毎朝、約2500人の日本人がキャンプから乗用車、ミニバス或いは工事用車輌にて現場に移動し、そこにアルジェリア人の乗った約100台の大型バスが乗り入れてくる、それはさながら日本の通勤ラッシュ時の見慣れた駅前の光景のようであった。
アルジェリア人のバス通勤には面白い話(当時はとても真面目な話であったが)がある。即ち、バスに乗り込む前に行われる出勤チェックを済ませるとバスに乗ることなく雲隠れするアルジェリア人が多く、それにどう対応するかが検討されたが、合理的且つ有効的な対策が見つからず、結局、バスコン(バスコントローラー)と呼ばれた日本人を毎早朝に夫々の町に派遣して一人一人のアルジェリア人の背中を押してバスに乗せると言う、到って原始的な方法での対応をせざるを得なかった。
アルジェ空港とハッシ・ロンメルの間は日本人の移動用として大型バスが毎日一便往復していた。このバスは新規赴任者或いは休暇明けの人が利用していたが、約2500人の日本人がいた現場であったので毎日20、30人がこのバスに乗車していた。 日本発のアンカレッジ経由パリ便のジャンボ機にて快適な空の旅を楽しみ、束の間のパリの空気を味わった後、オルリー空港からエアー・アルジェリーにてアルジェ空港に向かう。既にこのオルリー空港のロビーはパリの香りはせず、アルジェリアそのもの。大きな荷物を機内に持ち込もうとして職員に止められ興奮して叫んでいる人、搭乗のアナウンスと共に搭乗口に殺到する人、人、人(日本人はいつも気が付くと最後尾になっていた)。兎に角、大混乱の中、アルジェ空港に到着。オルリーから始まった苦難の旅はいよいよそのピークである600キロのバスの旅となる。
羊のミンチのサンドイッチと小さな錆びた缶のジュース1本を渡され、エアコン装備のないバスに押し込められ、約8時間のバス旅行が始まる。普通エアコンの無いバスは夏には窓を開け、冬は窓を閉めて走ると言うのが常識であるが、この地ではまったく逆であった。夏は窓を開けると外から熱風が吹き込むということで60度を越える鉄の箱の中じっと耐え、冬は運転手が眠くなるからというアルジェリア人らしい理由で窓をあけ、厳寒の夜道で新聞紙を身体に巻きつけ一晩中寒さに震えていた。当時現場で最も消費量(実際は損失だが)の多い物の一つが毛布であったことを後に知ったが、この厳寒のバス旅行対策だったようである。勿論今はこんなことは起こり得ないが。

ハッシルメルのプラント遠景
さらに大きな距離との戦いはティンフイエ・プロジェクトであった。現場はアルジェより1400キロ、最寄りの空港(ウワルグラ市)から600キロ、最も近い村まででも300キロに位置しており、且つ空港のあるウワルグラ市より午前中30分、午後30分の無線のみが唯一の通信手段(これとて砂嵐が吹けば全く不通となる)であったこのティンフイエは、まさに陸の孤島であった。
アラビア語で不毛の地という意味のサハラの荒涼たる土漠と忽然と現れる砂丘の間を縫うように走る道を睡魔と戦いながら車を走らせていると、かつてはこのサハラも海の底であり、その後は緑豊かな大地となって様々な動植物が生活を営んでいたことに思いを馳せ、砂と埃と汗にまみれた現場生活の現実とのあまりのギャップに"この地がかつての楽園のような所であったならどんなに仕事も楽しいことか"等と我知らず恨み言を言っている自分に気がつくこともしばしばであった。
単調な道だったが故に、当時は空港と現場間の約600キロをいかに早く走ったかを自慢していたものだが、これには二つの大きなリスクがあった。 第一のリスクは、この約600キロの間にはガソリンスタンドが1軒しかなく、時速150キロを越す走行を続けると途中ガス欠をおこし徒歩(運がよければ通りかかった車に乗せてもらえるが)にてガソリンスタンドに救援を求めなければならない。車のガソリン消費量がいかにスピードと風に影響されるか思い知らされるわけである。
もう一つのリスクは道路上の穴による車の横転である。この穴は大型トレーラーによってつくられたもので深さが20センチに及ぶものもあり、この穴に高速で飛び込むとタイヤがバーストし横転するという大事故の危険があった。 当初は穴の直前で急ブレーキをかけるも間に合わず穴に落ちるという失敗を繰り返したが、馴れてくると穴の前のブレーキ跡が遠方から識別でき穴を回避出来るようになった。現場の駐在員がプラント建設用資材の輸送中のダメージを最小限に止めることを目的に穴マップなるものを作成しトラックの運転手達に渡したが、現地の人達も知らない道の穴マップを日本人が作ったことに多いに驚いていた。

果てしなくまっすぐな道
この約600キロのサハラの道で最も印象に残っているのは、車のトランスミッションが故障し砂漠での野営を強いられた時のことである。砂地に車を乗り入れ、時々エンジンをかけ暖をとりながら寒さと飢えをしのいでいたが夜明け前に軍隊の一個師団が通りかかり毛布と乾パンを置いていってくれた。

砂漠で困っている人をみたら必ず助けるという"砂漠の掟"があると聞いていたが砂漠で生きるとはこのことかと都会の無関心に慣れていた私は本来の人間の優しさに触れたようでこころを熱くしたものだ。
(以下次号へつづく)