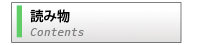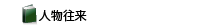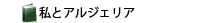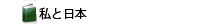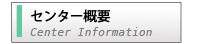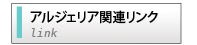|
ギー ペルヴィエ Guy Perville (著)
|
評者:中村 遥(上智大学大学院)
本書は、フランス側の視点から書かれたアルジェリア戦争の歴史である。アルジェリ ア戦争は、1954年から1962年の8年に及んだ。この戦争はアルジェリア、フランスどち らの視点から描くかで、異なる様相を呈してくる。筆者があえて「フランス側の視点」(ま えがき)としているのはそのためである。
アルジェリアは1830年にフランスの植民地となった。1871年にはフランス本国の延長 として内務省の管轄に組み込まれ、フランス人入植者の人口は100万人を超えた。この点 において、アルジェリアはフランス最大の植民地であったと言ってよい。
そのアルジェリアにおいて独立戦争が起こったのは1954年である。軍事的に劣位にあっ たアルジェリア側はゲリラ戦から始め、やがて国際世論に訴える戦法をとり、フランスに 対抗する。一方のフランスは、当初は「フランスのアルジェリア」の維持を望んだが、次 第に戦争は泥沼化し、ド=ゴール政権のもとアルジェリアの独立を承認するに至る。この 過程において、アルジェリア維持を望むフランス人たちがアルジェリア独立容認派と対立 し、フランスは内戦に近い状態となる。アルジェリア独立戦争は、フランス対アルジェリ ア、そしてフランス対フランスという二つの対立を含んでいた。
本書は、植民地時代から始まり、第四共和政、ド=ゴールに至るまでのフランス政治史 とアルジェリア戦争を丁寧に描いている。また戦争の過程においては、フランス対アルジ ェリア、そしてフランス対フランスという二つの対立を明確にしながら戦争の経過を明ら かにしている。著者の姿勢は冷静で、淡々と独立戦争を語る。そこにフランス・アルジェ リア双方の残虐行為の生々しさが表れることはない。
同時に著者は、随所においてアルジェリア側の動向も盛り込んでいる。独立戦争過程に おけるアルジェリアの内部抗争への言及や、犠牲者数は、アルジェリア・フランス側双方 に依拠した複数のデータを掲載している。他にもアルジェリア人でありながらフランス軍 に協力したハルキと呼ばれる人々、フランス本国と対立したアルジェリアのフランス人、 アルジェリアを支持したフランス人たちの様子も描かれる。こうした歴史の主体の多様さ や複数の視点を提示していることによって、アルジェリア独立戦争の複雑さが立体的に描 写される。
この本の構成は第九章からなる。この構成は大きく三つに分けることができる。第一章 から第三章までは、植民地時代から始まり、アルジェリア独立戦争が起こった原因につい て検討している。第四章から第八章はアルジェリアの武装蜂起とそれに対する本国政府の 反応、そしてド=ゴールのアルジェリア政策と和平交渉の経緯について述べる。最後の第 九章で独立まで至った戦争の総括と、その結果と影響について言及している。
また本書は、独立戦争後フランスに渡った大量のハルキ、ピエ・ノワールなどの引き揚 げ者、現在に通じる移民問題に対する意識も読者に向けて用意しているといえるだろう。 事情は異なっても旧宗主国である日本にとってこれは決して他人ごとではない。日本も植 民地支配をめぐり、韓国・中国と本当の和解ができているとはいえない状況におかれてい る。植民地支配の過去をめぐり、教科書問題、靖国参拝、慰安婦像建設のニュースが記憶 に新しい。
これは細やかで誠実に描かれたアルジェリア戦争の歴史である。本書はアルジェリアへ の理解にもつながるであろうし、現在のフランスが抱える問題について考える発露ともな ろう。しかし、日本の読者が本書を読むとき、その後に日本の植民地の問題について考え をめぐらせてほしいと思う。日本でもアルジェリアでも経験が「過去」になりつつある。 「戦争は終わったのだろうか」(第九章III節)、この問いかけは経験と過去の狭間にある 現在において重い意味を持つ。