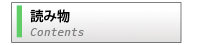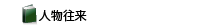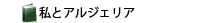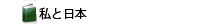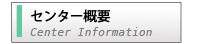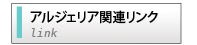明石書店、2009年、定価2,000円+税
評者:岩崎えり奈(共立女子大学)
・・・ここは地の果てアルジェリア、どうせカスバの夜に咲く・・・。この「カスバの女」の歌が流行った1960年代において、アルジェリアは日本人にとって心情的に近かったようだ。1962年には、石原裕次郎主演の映画「アラブの嵐」が公開され、その主題歌を「カスバの女」を作詞した大高ひさをが作詞し、石原裕次郎が次のように歌った(1)。
「赤い夕日に燃えている、俺の心とピラミッド、ナイルの岸を血に染めて、男同士の祖国愛、ああ命 命懸けなら 俺もやる、狭い日本の東京の、俺は嫌だぜ熱帯魚、アラブの嵐吹きすさぶ、男同士の祖国愛・・・」(注:映画の舞台はエジプトだが、「祖国愛」はアルジェリアを指していたそうである)。
日本アルジェリア協会の前身である日本北アフリカ協会が設立されたのも、1960年代初頭(1961年)である(本著第45章)。また、1960年と1965年には、中東に関する日本の報道記事のなかで、アルジェリアに関する記事が最も多かったという(本著第44章)。
言うまでもなく、当時の日本でアルジェリアが脚光を浴びたのは、第三世界の反帝国主義、反植民地主義や民族主義の高まりという国際的な政治社会状況が背景にある。本著の執筆者の何人かも、アラブ民族主義の旗手としてのアルジェリアに魅力を感じて、アルジェリアとマグリブの研究の道に入った世代である。
ところが、その後、民族主義の気運が盛り下がるとともに、アルジェリアは日本人にとって遠い国になってしまった。今の日本では、アルジェリアに関する情報は非常に少ない。政治に関するいくつかの本をのぞけば、一般読者向けのアルジェリアに関する書物はほとんど皆無である。そうした情報の欠如が、「カスバ」などの異国情緒か、イスラーム「原理主義」やテロで危険といった偏ったイメージを助長している。
本著は単なるアルジェリア紹介にとどまらず、こうした断片的なアルジェリア社会像を排し、アルジェリア社会をその内側から理解しようとする意欲的なアルジェリア入門書である。従来の歴史観では、アルジェリアの歴史は近世までのアラブ・イスラーム史と植民地化を起点とする近現代史に分断されてきた。これに対して、本著は、「はじめに」で述べられているように、次のような特色をもつ。第一にフランス経由の情報に依拠するのではなく現地の情報を重視し、第二に植民地化と対仏独立戦争をアルジェリア史の基点にするのではなく、古代から現代まで通時的にアルジェリアの歴史を捉え、第三にアルジェリアをアラブ・イスラームの一員として描いていることである。
全体の構成は9部62章からなる。第1部の「自然環境と生態」は多様な気候風土と民族構成を、第二部の「謎に包まれた古代史」はサハラの古代文明やフェニキア・ローマの歴史を、第三部の「イスラーム文明の時代」は中世都市のトレムセンの繁栄や海賊とドンキホーテの意外な関係などを描いている。そして、第四部の「フランス植民地統治の時代」の後に、第五部の「独立と国家建設の歩み」はアルジェリア戦争の後遺症、社会主義の挫折とイスラーム「原理主義」の台頭を、第6部の「現代の政治と経済」は石油資源や政治、NGOや家族法論争などを、第7部の「国際関係のなかのアルジェリア」はアラブ世界やアフリカ諸国、EUなどとの関係を、第8部の「日本とアルジェリア」はアルジェリアで活躍した日本人ビジネスマンの目を通した日本とアルジェリアの関係を述べている。最後の第9部「日常生活にみえるアルジェリア文化」は文学や映画、ワインなどについてである。執筆者は全部で17人。研究者だけでなく、アルジェリア駐在経験のあるビジネスマンも執筆に加わっている。
それぞれの章は特定のトピックを扱っているので、どの章から読み始めても楽しい。しかし、どの章から読み始めたとしても、読者はアラブ・イスラーム的な文化伝統に根ざしたアルジェリア社会の豊かさを理解することになるだろう。と同時に、植民地支配がアルジェリア社会に与えた痕跡の深さを実感するだろう。
(1)阿部政雄「石原裕次郎主演の『アラブの嵐』の背景にアルジェリア独立運動」
(日本アルジェリアセンターHP)