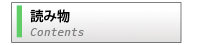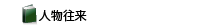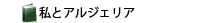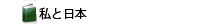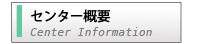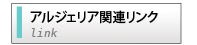評者:吉田 敦
1954年11月30日、9名の無名な青年によって決起され、7年半の間に甚大な人的被害をもたらしたアルジェリア独立戦争とは、いったい何であったのか。本書は、同国の政治的独立後、40年以上の歳月を経た現在から、その歴史的過程を通覧したうえで第三世界諸国に通低する挫折の要因を究明している。
アルジェリアは70年代、サハラ砂漠で発見された膨大な炭化水素資源の輸出収益を梃子に急速な工業化を達成し、第三世界諸国の輝ける星として世界中の注目を浴びた。本書でも引用されているように、当時のブーメディエン大統領は、急進的な国有化政策を掲げて以下のように述べている。「革命的権力に課せられている緊急任務は、社会主義を達成するために前もって行うべき諸条件を整えることである。すなわち、安定した揺るぎない国家を建設し、革命の諸目的を実現するために必要不可欠とされる手段を獲得し、民族の富を奪い返し、経済を建設し、企業の財政状態を改善して利益を増大させなければならない。かくしてアルジェリアは、独立を揺るぎないものとし、社会主義経済発展の基礎を創設し、経済に対する支配を強化することができる」(本書、110ページ)。
しかし80年代、アルジェリアの壮大な開発計画は、膨大な累積債務のなかで完全に挫折していった。アルジェリアを襲った未曾有の経済危機のなかで、さらに90年代、同国では凄惨なテロ旋風が吹き荒れる。著者も同意しているように、アルジェリアにとって90年代の暗黒の時代はまさに「失われた10年」そのものであった。
1999年、現在の大統領であるブーテフリカ大統領が就任して以来、アルジェリアは新しい時代を迎えたといわれている。同大統領は、経済面では市場経済の導入(民営化政策)と国際社会への復帰(EUとの協力協定締結、WTO加盟)を積極的に図っている。政治面では、テロ活動の中核を担ったイスラーム救国戦線(FIS:Front Islamique du Salut)を武力によって根絶、さらに最近では「市民融和法」(concorde civile)と呼ばれる恩赦法を発布してテロ実行犯に対する一定の理解を示した。
しかしその一方で、同国の失業問題、貧富の格差、地域格差、産業基盤は不在のままであり、アルジェリアが抱えてきた根源的な問題は一向に解消されていない。この点について、著者は以下のように指摘している。「IMFが財政破綻に陥った途上国政府の救済策として打ち出している市場経済の導入、緊縮財政、民営化政策は、マクロ経済を安定させても、貧富の格差を拡大し、社会的不安を増大させている。輸入代替工業化を推進するためにとられた余りにも手厚い関税システムが、アルジェリア経済を崩壊へと導いたのではなく、炭化水素収益を私物化し腐敗の極限にまで至らしめたFLN独裁体制が選択した杜撰な開発政策にこそアルジェリア経済崩壊の要因を求めるべきではないだろうか」(本書、249ページ)。
本書は、アルジェリアを愛するがゆえに、その根源的な疑問に対する回答を求めて行きぬいた著者の30年間におよび情熱の軌跡である。本書ではFLN独占体制が抱える権力構造の分析までは触れられていないが、少なくとも「新生アルジェリア」として生まれ変わろうとしているアルジェリアの未来を見渡すうえで重要な指針となる研究書であることに間違いはない。