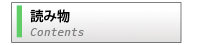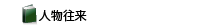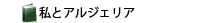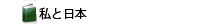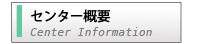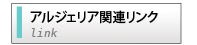渡辺 伸著
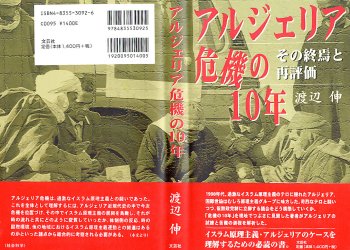
2002年6月
北村 美都穂
私がこの本の存在を知って数日後に著者は死去され、福田邦夫さんが「著者に代わって」贈ってくださいました。1996年から2001年まで駐アルジェリア大使を勤めた著者は、「危機」の最終局面を現地で観察して、日本(だけでなく「先進」諸国)では、「軍事独裁政権と民主勢力との闘い」という、 おもにフランス経由の一面的な観点でしか報道されていないアルジェリアの状況を、正しく日本に伝えたいとの思いから、「任国の政治を論評しない」という外交官のマナーにそむいて、ペンネームで日本の中東問題専門誌に寄稿を続けました。それをもとに編まれたのがこの本です。
私は、A.ホーンという英国人によるアルジェリア独立戦争史を翻訳して1994年に上梓(『サハラの砂・オーレスの石』)しましたが、「危機」が顕在化する前の'80年代前半までのことしか扱われていないので、訳書には宮治一雄さんにお願いして、'94年初め頃までの状況を補足していただきました。今にして思えば、ちょうどその頃から「危機」は収束に向かい始めていたのでしたが、当時は知る由もありませんでした。
渡辺氏の本の情報源は、アルジェリアで発行されているフランス語・アラブ語の新聞およびそれらの記者、各国とくにアラブ・アフリカ諸国の駐アルジェリア大使など、日本のメディアには紹介されること少ないものが主で、従来流布されていたのとはかなり違う様相が語られています。「軍事独裁政権」下のアルジェリアで、反政府的論調のものを含め多数の新聞が発行されつづけたというのも驚きですし、体制崩壊の危機に直面した政権が、法治国家秩序を可能なかぎり維持しつつ、当初約束した日程に沿って、憲法改定、複数政党制による議会選挙実施を通じ、大統領選挙により体制を再建するにいたる過程も認識を改めさせるものがあります。
とくに私の訳書刊行後に刊行された当事者の回顧などを通じて、独立前後の事情が明らかにされていることには興味深く感じました。 この本が「政権寄り」と評価されうであろうことは著者自身も危惧しているところですし、正直のところ私にもその感は否めません。しかし、これまで流布されてきた見方も一面的であったことを教えられたのでした。
ところが、5月末に行われた総選挙では、カビリー地方の少数民族を基盤とする野党勢力がボイコットし、投票率は50パーセントを割ったと報じられました。独立戦争中から底流に伏在し、ときに顕在化していた民族問題が再燃しているということでしょうか。
私は訳書の「あとがき」を、「この困難な独立革命を戦いぬいたアルジェリア国民の英知と忍耐が、いつの日か必ず"アルジェリアのものである解決"を見出すであろうことを希っている」と結んだのでしたが、それが見当違いではないことをあらためて希うものです。
国民のアルジェリアと権力者たちのアルジェリア
-望むことと可能なこと
モハメッド・タメルト
アラビア語日刊紙アル・ハバル元記者
フリージャーナリスト
数年前、引退したハーレッド・ネッザール将軍は私に次のような質問をした。
「もし我々が1991年の国民議会選挙を中断していなかったらなにがどう変わっていただろうか。イスラミスト達はその時すでに政府に対するジハードの呼びかけを準備していたのに。」
私はこう答えた。「中断しなかった場合との違いは数字だけです。 死者10万人という」
しかし、10年にわたったアルジェリアの政治と治安上の危機を振り返ると、1991年に国民が出した選択を、もし権力側が尊重していれば暴力がこれほどの痕跡を残すことはなかったであろう。暴力は国民の精神的、財政的、またロジスティックな援助なくしては政治的圧力になることはないし、現に、マスコミが武装グループの狂気の沙汰を内部からの情報を得て大々的に報道するまでこの援助は続いたのである。
アルジェリア国家を揺さぶりつづけるために暴力に理想的な環境があったと政界と軍関係者は告白する。しかし、彼らはこの現実と1992年1月の選挙プロセスの中断という致命的な間違いとの本質的な関係については一切語ろうとしない。
10年後、アルジェリアの政権は2度目の間違いを起こしつつあることに気づいていない。今、政府が相手にしているのはイスラミストとではなくカビールの人々であるが状況はほとんど同じであるし、実際、問われているのは1992年と同様、国の民主化である。
数年後、私が英国に発つ2001年9月の寸前、アブデルアジズ・ブーテフリカ大統領の顧問と議論したことがある。私は政党と政権の間には真の対話が不可欠であること、そしてアルジェリアの問題を解決するには選挙工作や国家の暴力を使って政権を保つことを考えるのはやめにしないといけないと言った。 先方の話の内容からブーテフリカ大統領が"アールーシュ"(カビール地方で暴力を極端まで押し進めている秘密勢力)との対話を準備していると解ったとき、私は、そんなグループよりFFS(社会主義勢力戦線:カビール地方で最大の政党)のような政党と対話する方がずっと大事だと言った。
また、先の大統領選に立候補し、3百万票を集めたが最終的にリタイアしたターレブ・イブラヒミが率いるエル・ワファという政党がある。元駐日大使だったヌーレディーン・ゼルフーニ現内務大臣と当然のことながら大統領もこの政党を認可していないが、私はその大統領顧問にこのような影響力のある政治勢力と対話することが大事だと大統領に伝えてくれるよう頼んだ。
それから6ヶ月たち、事態は変わらず、全体的な解決にまだ目処がたたない今、私は自問する。 「一体政権はなにを望むのか?バトナからティジウズ、オランからコンスタンティーヌ、アルジェからタマンラセットに生きるアルジェリアの人々は何を望むのだろう?どうしたら二つの岸を渡し、妥当な線で歩み寄れるのだろうか?
アルジェリアの国民の望みは高い。しかし、もし権力者たちが実際に政治や経済に改革を始めるならば、国民は政府を信頼するだろう。 しかし、反対に国民をだますことはできないし、うそを納得しろといってもそうはいかない。 残念なことに、今まで権力側はそうしてきたし、今の大統領でもそのやりかたを変えることはできていない。
解決に達するためには妥協が必要だが、数年の危機をくぐってきたにもかかわらず、権力側はそこを理解していない。もはや、理解しなければいけないときである。 権力者達のアルジェリアは、恐怖から遠く離れた"クラブ・デ・パン"のコンパウンドに住む守られた子供達のことよりも国全体の子供達のことを考えなければならない。 政治的解決は包括的でなければならず、部分的であったり、表面的であってはならない。 意識改革をすべきは、緑の制服を着た人達や、その周りにいる影響力のある民間人という、実際の権力者たちである。
若い国の指導者は若い人であるべきであり、ずっと前にくず鉄にされていいような古い荷車に引かれていてはいけない。 現在の状況はアルジェリアにはふさわしくない。 国の未来はその国の若者によって決められるべきであり、そしてその未来は近隣諸国や、より広い地域の国々の未来にも影響を与える。 このような事実を考慮するときが来ているし、いかなる改革も奨励するべきである。 この日本の読者に向けた論文には以下の結論がもっともふさわしいと思う。
- 我々アルジェリア人と日本人は実に良い関係にある。
- あなた達日本人は、我が国に投資をしている。腐敗や官僚主義によってほとんど途絶えてしまった改革を政治的に無理ならば、経済の面からふたたび生き返らせて欲しい。
日本アラブ協会発行「アラブ・夏号」から転載
渡辺伸 前大使を偲んで
2002年7月2日
伊藤忠商事(株)長谷川善郎
渡辺さんは亡くなられる前日、来日中のアルジェリア外務省のベレクシ・アジア局長との会談用資料を自宅で作成中に突然倒れられた。しかし、入院先の病床で奥様に口述筆記を頼んで資料の完成を急がれたと聞く。日本とアルジェリアの掛け橋として全力を尽くされた渡辺さんらしい壮絶なご最後だったとしみじみ思う。
渡辺さんが1996年アルジェリアに赴任された時のこと、ゼルーアル大統領(当時)に信任状を奉呈された後TVのインタビューを受け、その際、流暢なアラビア語で応対された。これが現地の人々の間で話題になり、われわれ日本企業関係者も何か"新しい風"を予感する驚きがあった。それから数ヶ月後、「アルジェリアは軍事独裁政権か」と題するレポートを発表された。それまで窺い知れなかったアルジェリア権力構造の実態を解き明かした内容に、われわれはまさに感嘆した。
渡辺さんはそれからも次々と文章を発表されて、今年1月、『アルジェリア危機の10年−その終焉と再評価』(文芸社)の1冊に纏められ、予想に違わぬ高い評価を得た。
渡辺さんが赴任された当時、アルジェリアは独立後最大の危機から立ち直ろうとしていた時期だった。すでに欧米の政府要人やビジネスマンは商談機会を求めて頻繁にアルジェリア詣でを始めていた。渡辺さんは欧米勢に遅れをとってはと絶えずわれわれを励まし、また日本企業のプラント現場にも積極的に足を運び、アルジェリア政府・公団に日本の技術をPRしていただいた。2000年11月には、7年振りに日本から民間経済使節団がアルジェリアを訪問したが、渡辺さんは使節団派遣の旗振り役でもあった。
昨年3月、渡辺さんがアルジェリアを離任された日、ちょうどアルジェリアに出張中だった私は同じフライトに乗り合わせた。渡辺さんは「昨日、ブーテフリカ大統領にお別れの挨拶をしてきました」と話されたまま、じっと窓から眼下に広がるアルジェリアの野山を見つめておられた。去来する思い出を一つ一つ確かめているような姿が今も私の瞼に焼きついている。