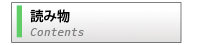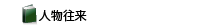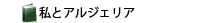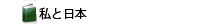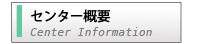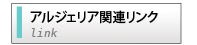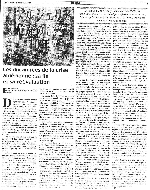アルジェリア危機の10年―その終焉と再評価
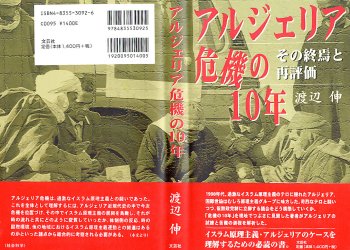 著者 渡辺 伸
著者 渡辺 伸
2002年1月20日 初版第1刷発行
株式会社 文芸社
〒160−0022
東京都新宿区新宿1−10−1
電話 03−5369−1960
FAX 03−5369−1961
アルジェリア危機の10年―その終焉と再評価(批評)
長谷川善郎(伊藤忠商事)
1990年代、アルジェリアはイスラム原理主義のテロに揺れた。本書は「アルジェリア危機の10年は何であったのか」と問いかけ、その実態を克明に分析して解き明かしている。
著者はアラビストで、1996年8月から2001年3月までの4年半、駐アルジェリア大使を務められた渡辺伸氏。「日本−アルジェリア センター」の主宰者でもある。
アルジェリアは長く苦しい植民地独立闘争を闘い、1962年に独立を勝ちとるが、その後の長きに亘るFLN一党独裁体制の宿弊がイスラム原理主義を一挙に噴出させた。
アルジェリア近現代史の中でこの危機の10年を位置づけ、その中でイスラム原理主義の展開を鳥瞰し、それが時の流れと共にどのように変質していったか、体制側の対応、時の国際環境、他の地域におけるイスラム原理主義運動との関連について丹念に事実を追い求めている。
同時に、著者はアルジェリアに関する我が国メディアを含めた国際報道のゆがみを厳しく問題にしている。
また、著者がアルジェリア在勤時に折に触れて記述した現地情勢が挿話としてちりばめられており、親しみが持てて読みやすい。巻末には時節柄、「ビンラーデン・グループとアルジェリアのイスラム原理主義」と題した補記も付いており、アルジェリアからのアフガン義勇兵の実態について、ここでも著者の鋭い観察眼がある。
全巻を通じ、アルジェリアをよりよく理解し、その実像を外に知らせようとの著者の気持ちが伝わってくる。
アルジェリアについての我が国での最初の本格的書き物として、今を去る30年前、植民地独立闘争の苦闘を著した「アルジェリア革命―解放の歴史」(刀江書院 1972年 淡徳三郎著)が出版され、好評を博した。歴史は連続であり、本書「アルジェリア危機の10年―その終焉と再評価」はその後のこの国の歴史を見事に継承している。
アルジェリア研究者のみならず、中東研究者にも是非ご一読をお勧めしたい一冊である。
(2002.1.18)
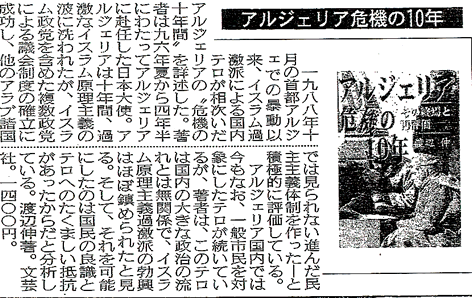
サンケイ新聞 2002年2月15日朝刊「本の紹介と批評欄」より
●本書のアルジェリアにおける反響:
Liberte誌 La Nouvelle Republique 誌
講談社刊行 「週刊 世界遺産 アルジェリア アルジェのカスバ」

2002年1月3日発行
講談社「週刊 世界遺産」
とにかく、見て読んで文句なしに楽しい写真集である。アルジェリアに関してはこの種の出版物がここ10年くらい皆無であっただけに貴重である。「ここは地の果てアルジェリア」の暗く、もの悲しいイメージを変える、明るくバラエティに富んだ、奧の深いアルジェリアが紹介されている。北アフリカからサハラに広がるこの雄壮な国への旅心がかき立てられる。(編集部)
講談社
東京都文京区音羽2−12−21
販売問合せ 電話03−5395−3604
<特別寄稿>随想 日本人と異文化
久米邦貞(前駐独大使)
(本稿は、<FEC(国際親善協会)NEWS> 2月号に掲載されたものであるが、この国際化の時代に、かえって外国勤務の日本人の現地社会との交流が難しくなっていることを指摘した考えさせられるところの多い随想的書き物である。協会のご好意でここに掲載させていただくことにした。協会に御礼申し上げる。)
一九九八年から三年間の駐独大使時代、最近のドイツ各界の対日関心の急速な低下を痛感しつつ、各地での講演等の機会に対日関係の重要性への認識を高めるべく努めてきたが、そうした際に聴衆の中から逆に度々指摘されたのが最近の在独在留邦人のドイツ文化に対する無関心と、地元社会との交流への意欲の低下である。海外進出企業による現地社会への利益還元や赴任者の地元社会との融和に向けた努力の重要性が日本で強調されるようになって既に久しく、その間に多くの改善もなされて来たのを記憶しているだけに、昨今の急速な国際化が進む中でこうした指摘を各地で受けたことは意外であり、残念に思えた。
ドイツ各地に駐在する日系企業の関係者に聞くとこの背景にはいくつかの事情があるようだ。先ずはリストラによる人員削減や若返り、業績重視の風潮もあり、大世帯の邦人社員を抱えた現地本社の幹部等を除くと多くの駐在員は、本業第一で地元社会との交流まではとても手が廻らない。地元とのパイプの構築は長い目出見ればビジネスの上でも利点となるのは承知でも、ビジネス活動の広域化に伴い、この利点も相対的に意義が低下している。各国でも国際化が進んだ結果、仕事は以前とは異なってすべて英語で事足り、地域社会との交流に必要な現地語の修得や現地事情のフォローに費やす時間は勿体ない等々の事情である。
さらには最近の国際化そのものが海外の法人と現地社会との間の距離を拡げる原因となっている面も見逃せない。かつての五十年代六十年代とは異り今日では、各地の邦人社会も飛躍的に成長し、日本人学校や日本食店も至る所にあって海外生活とは言っても本人の心がけ次第では毎日でも日本人同志で寄り合い、日本の新聞や日本のテレビのみを見て国内と変わらない暮らしをすることも可能な時代となっている。
かつてのように懸命の努力によって現地の言語を修得し、現地の文化社会に飛び込まなければ外国暮らしはできなかった時代は過ぎ去っており、それだけに現地の社会に溶け込むためには本人が余程の心がけをもち、自ら努力をすることが必要な時代となっている。一時の観光客は別としても、異文化に接し、異質の社会を体験することによって自らの世界を拡げるまたとない機会を与えられることになる海外赴任者がこの折角の機会を活用しないのはいささか残念なことである。
航空機の発達による外国旅行の簡易化や情報通信メディアの普及によって皮相かつ断片的なものとは言え外国に関する情報が飛躍的に増大していること、また共通語としての英語や情報技術を使っての各国の人々との意思疎通や事務処理が急速に容易になりつつあることはそれ自体大いに結構なことである。しかしその反面で各国各地域の人々の心の根幹にある夫々の文化、思想、価値観と言ったものを理解しようとする努力が蔑ろにされるとすれば、異文化間の相互理解はむしろ後退することとなり、真の意味での国際化には寄与しないだろう。